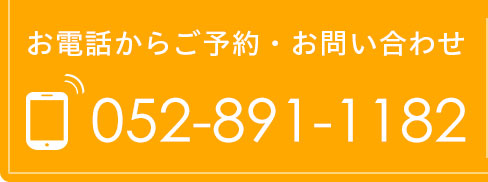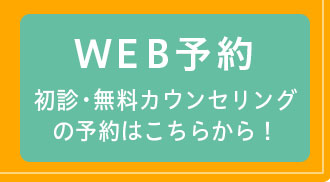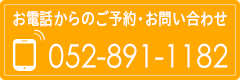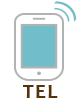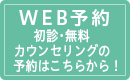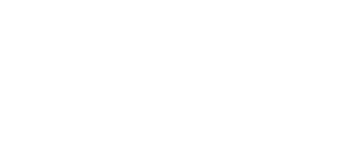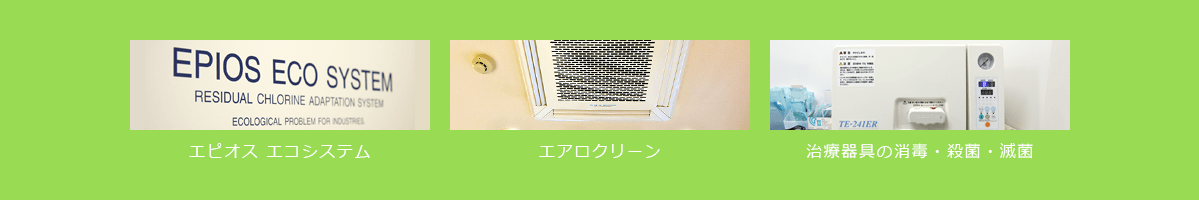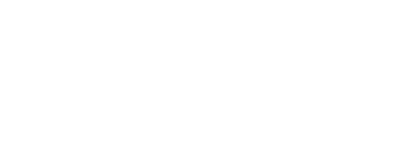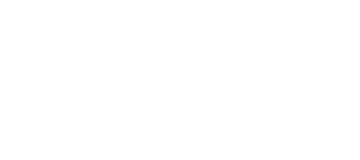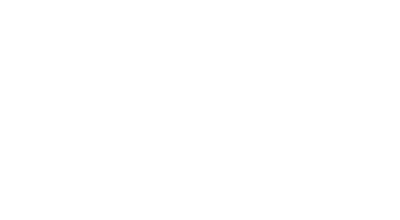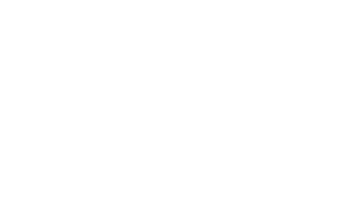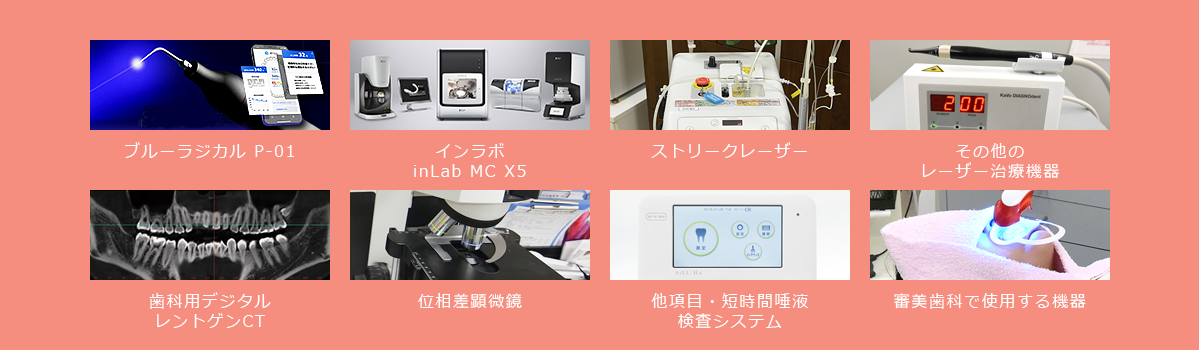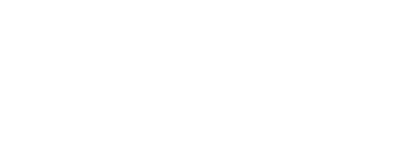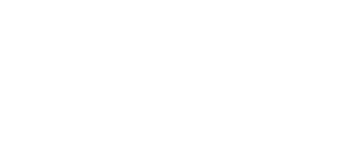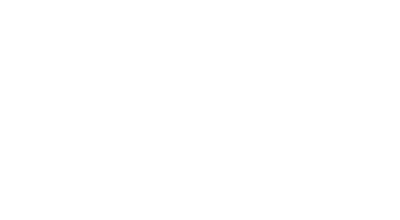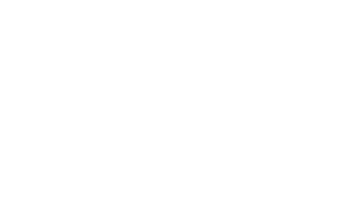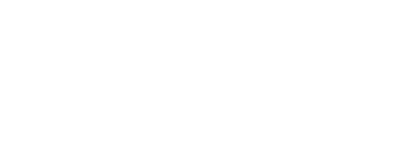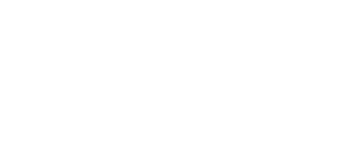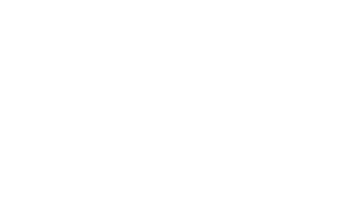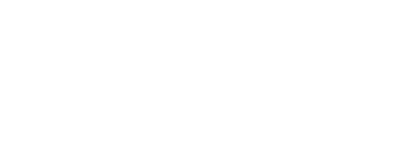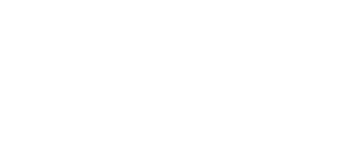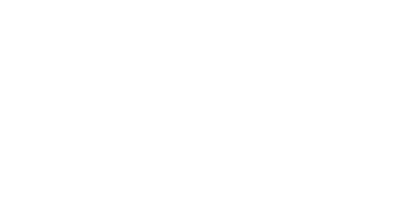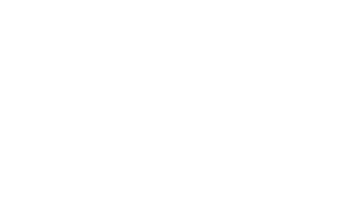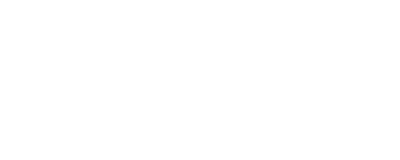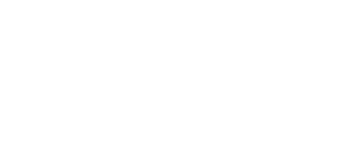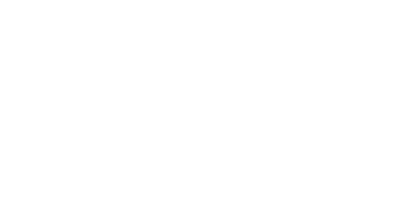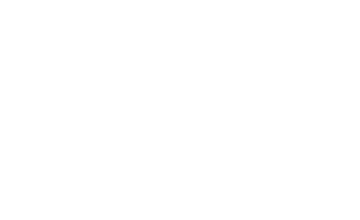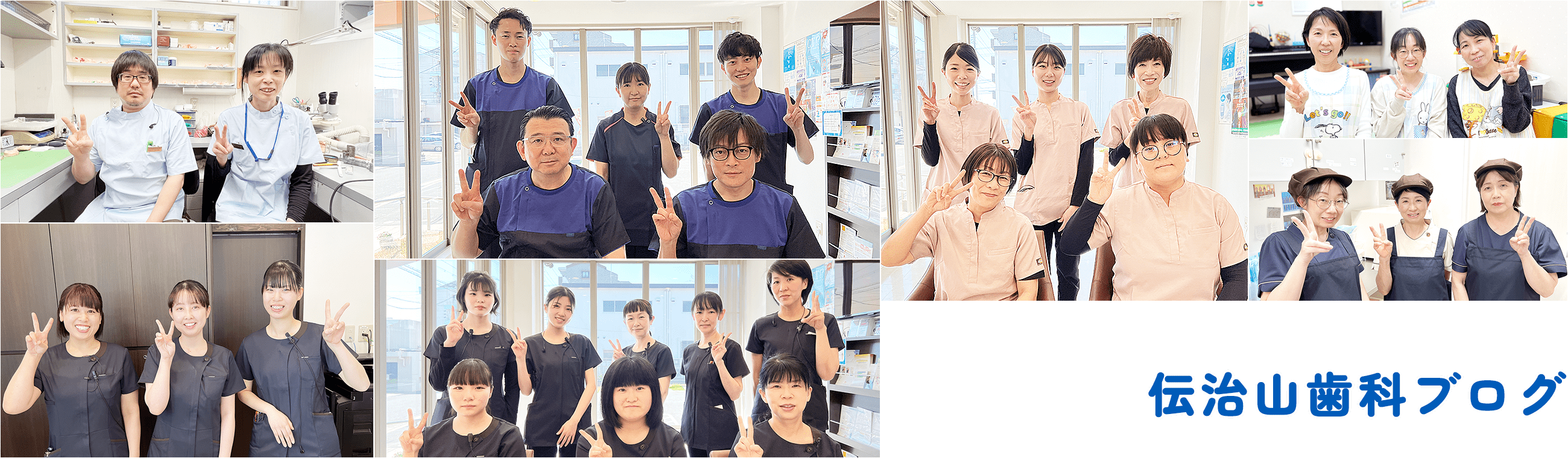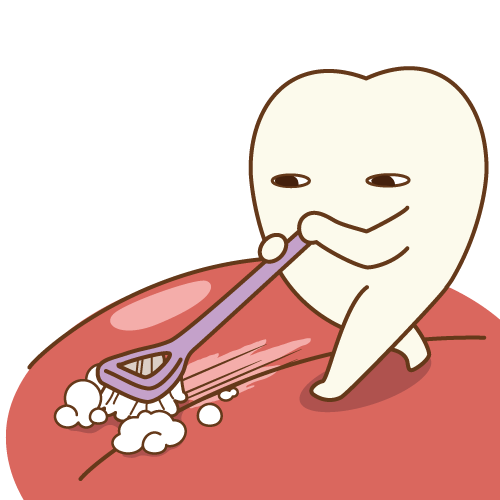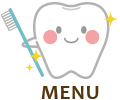誤嚥性肺炎の歯科的予防:口腔ケアと摂食嚥下機能の維持が鍵
誤嚥性肺炎とは
誤嚥性肺炎は、飲食物や唾液、胃液などが誤って気道に入り込む「誤嚥」によって引き起こされる肺炎の一種です。特に高齢者や、脳血管障害、神経筋疾患、認知症などの基礎疾患を持つ方々に多く見られます。誤嚥によって気道に侵入した口腔内の細菌が肺で増殖し、炎症を起こすことが主な原因です。この病態は、発熱や咳、呼吸困難といった典型的な肺炎症状に加え、時に無症状で進行し、気づかないうちに重症化する「不顕性誤嚥」も問題となります。
誤嚥性肺炎の予防は、単なる医療行為に留まらず、日常生活の質(QOL)を維持し、健康寿命を延伸するための重要な課題です。そして、その予防において、歯科が果たす役割は極めて大きいことが近年明らかになっています。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の温床は、他ならぬ口腔内にあるからです。本稿では、歯科的アプローチによる誤嚥性肺炎の予防策を、多角的に詳細に解説します。
1. 口腔内の細菌数を減らす:徹底した口腔ケア
誤嚥性肺炎の最大の原因の一つは、口腔内の細菌です。健康な人の口腔内には数百種類、数十億個もの細菌が存在し、これらは日常の飲食や唾液の分泌によって絶えず増えたり減ったりしています。しかし、口腔ケアが不十分になると、細菌の塊である「歯垢(プラーク)」や「舌苔」が形成され、これらの細菌が誤嚥時に気道に侵入し、肺炎を引き起こすリスクを高めます。
1.1. 専門的な口腔ケア(プロフェッショナルケア)
歯科医院での定期的な口腔ケアは、誤嚥性肺炎予防の最も効果的な手段です。
- 歯周病治療と歯石除去: 歯周ポケットには、誤嚥性肺炎の原因となる細菌が豊富に存在します。歯科衛生士による専門的なクリーニング(PMTC:Professional Mechanical Tooth Cleaning)は、日常の歯磨きでは除去しきれない歯垢や歯石を徹底的に除去し、歯周病の進行を抑制します。
- 義歯(入れ歯)の清掃指導と調整: 義歯の表面には、口腔内の細菌が付着しやすく。特に、義歯の下には真菌の一種であるカンジダ菌が増殖しやすく、誤嚥性肺炎のリスクを高めることが指摘されています。歯科医師や歯科衛生士による適切な義歯清掃指導、そして義歯の適合性を定期的にチェック・調整することで、義歯による口腔衛生悪化を防ぎます。
- 舌苔(ぜったい)の除去: 舌の表面に付着する白い苔のような「舌苔」も、多くの細菌を含んでいます。高齢者や口腔機能が低下した方では、舌の動きが悪くなるため自浄作用が低下し、舌苔が増加しやすくなります。歯科衛生士による専用の舌ブラシや舌クリーナーを用いた舌清掃の指導は、口腔内の細菌数を減らす上で非常に有効です。
1.2. 日常的な口腔ケア(セルフケア)
歯科専門家によるケアに加え、患者さん自身や介護者による毎日の口腔ケアが不可欠です。
- 歯磨き: 歯ブラシはヘッドの小さいものを選び、歯と歯肉の境目、歯と歯の間を丁寧に磨きます。特に、奥歯や磨き残しが多い部位を意識して磨くことが重要です。
- 義歯の清掃: 義歯は食後、必ず外して流水で洗い、専用のブラシと義歯洗浄剤を使用して汚れを落とします。就寝時には外して保管し、口腔内を休ませることも大切です。
- 舌の清掃: 舌ブラシやガーゼ、スポンジブラシなどを用いて、舌の奥から手前に向かって優しく汚れをかき出します。力を入れすぎると舌を傷つけるため、注意が必要です。
2. 摂食嚥下機能の維持・向上:口腔機能訓練の重要性
誤嚥は、単に口腔内の細菌が問題となるだけでなく、食べ物や唾液をうまく飲み込むことができない「嚥下機能の低下」が直接的な原因となります。歯科医療では、この嚥下機能を維持・向上させるためのアプローチも積極的に行っています。
2.1. 嚥下機能の評価とリハビリテーション
- 口腔機能のチェック: 歯科医院では、舌の動き、唇の閉鎖力、咀嚼能力、唾液の分泌量などを評価する専門的な検査が行われます。これらの評価を通じて、嚥下障害の有無や程度を把握します。
- 嚥下訓練の指導: 歯科医師や歯科衛生士は、口腔機能の低下を補うための様々な訓練を指導します。
- パタカラ体操: 「パ」「タ」「カ」「ラ」と発声することで、唇や舌の動きを強化する訓練です。これらの音は、それぞれ「パ(唇)」「タ(舌先)」「カ(舌の奥)」「ラ(舌)」の筋肉を効率よく鍛えることができます。
- 咀嚼訓練: 咀嚼筋を鍛えるために、ガムを噛む、乾燥昆布を噛むなどの訓練も有効です。
- 嚥下筋群のストレッチ: 首や肩の筋肉をほぐし、嚥下に関わる筋肉の柔軟性を高めるストレッチも指導されます。
2.2. 義歯の適合性:咀嚼と嚥下の土台
適切に調整されていない義歯は、咀嚼効率を低下させるだけでなく、誤嚥のリスクを高めます。
- 咀嚼効率の低下: 合わない義歯は、食べ物を十分に細かく噛み砕くことができず、大きな塊のまま飲み込むことになり、誤嚥の危険性を高めます。
- 口腔内の違和感: 違和感のある義歯は、唾液の分泌量や唾液腺からの唾液の出方にも影響を与え、口腔内の乾燥を引き起こすことがあります。
- 定期的なチェック: 義歯は、歯ぐきの変化によって時間の経過とともに適合性が悪くなります。定期的に歯科医院でチェックを受け、必要に応じて調整や修理、作り直しを行うことが、適切な咀嚼と嚥下を維持する上で不可欠です。
3. ドライマウス対策:唾液の役割
唾液には、口腔内の細菌を洗い流す「自浄作用」、細菌の増殖を抑制する「抗菌作用」、そして食べ物をまとまりやすくする「潤滑作用」があります。しかし、加齢や薬剤の副作用、脱水などにより唾液の分泌量が低下する「ドライマウス(口腔乾燥症)」は、これらの重要な機能が損なわれるため、誤嚥性肺炎のリスクを高めます。
3.1. 唾液腺マッサージ
唾液腺を刺激することで、唾液の分泌を促すことができます。
- 耳下腺: 耳たぶの少し下、頬の柔らかい部分を指でやさしく回すようにマッサージします。
- 顎下腺: あごの骨の内側の柔らかい部分を、下から上に向かって指で押すようにマッサージします。
- 舌下腺: 顎の先、下あごの骨の裏側を、舌を上顎につけながら指で押します。
3.2. 保湿剤や人工唾液の活用
マッサージだけでは十分な唾液が出ない場合、口腔用の保湿ジェルやスプレー、あるいは人工唾液などを使用することで、口腔内を潤し、誤嚥のリスクを軽減できます。これらも歯科医師や歯科衛生士に相談し、適切な製品を選ぶことが重要です。
4. 多職種連携:歯科医師、歯科衛生士、医師、看護師、管理栄養士、介護福祉士
誤嚥性肺炎の予防は、歯科単独で完結するものではありません。患者さんの全身状態、栄養状態、生活環境などを総合的に把握し、適切な予防策を講じるためには、多職種連携が不可欠です。
- 歯科医師・歯科衛生士: 口腔ケアと嚥下機能訓練の専門家として中心的な役割を担います。
- 医師・看護師: 全身疾患の管理、嚥下機能の医学的評価、誤嚥のサインの早期発見を行います。
- 管理栄養士: 嚥下しやすい食事形態の提案や、栄養状態の改善指導を行います。
- 理学療法士・作業療法士: 姿勢の調整や嚥下に関わる全身の機能訓練をサポートします。
- 介護福祉士: 毎日の食事介助や口腔ケアの実践において、重要な役割を担います。
これらの専門職が連携し、情報共有を行うことで、患者さん一人ひとりの状態に合わせた、より効果的な予防プログラムを確立することができます。
結び:歯科から始める健康寿命の延伸
誤嚥性肺炎は、高齢者の死因の上位を占める重大な疾患であり、その予防は超高齢社会における喫緊の課題です。本稿で述べたように、口腔内の細菌数を減らす徹底した口腔ケア、そして摂食嚥下機能を維持・向上させるための訓練は、誤嚥性肺炎予防の二つの柱となります。
「たかがお口のケア」と思われがちですが、口腔は全身の健康の入り口です。歯科による予防的アプローチは、誤嚥性肺炎のリスクを減らすだけでなく、歯周病や虫歯を予防し、おいしく食べられる喜びを維持することにもつながります。これは、単に病気を防ぐだけでなく、生活の質そのものを向上させることに他なりません。
歯科医院を「歯が痛くなってから行く場所」ではなく、「健康を維持するために定期的に通う場所」と捉える意識改革が、私たち一人ひとりの健康寿命を延ばす鍵となります。歯科医師や歯科衛生士は、誤嚥性肺炎の予防を重要なミッションと位置づけ、今後もより質の高い口腔ケアと嚥下指導を提供していくことが求められます。そして、その取り組みは、間違いなく日本の健康長寿社会の実現に大きく貢献するでしょう。